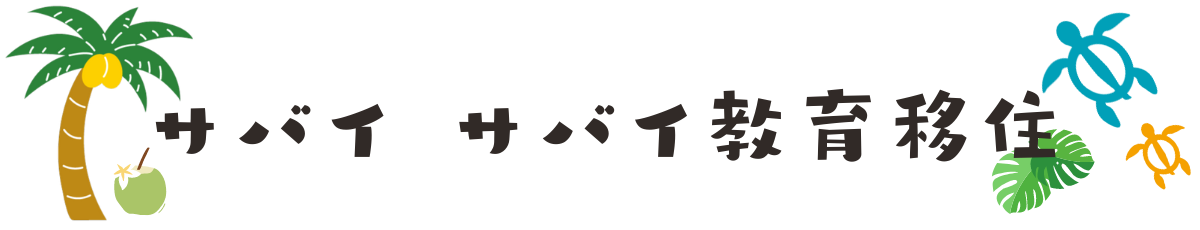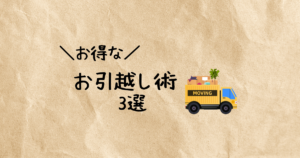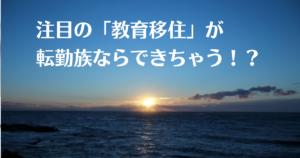こんにちは。教育系ブロガーのばるママです。
わが家は転勤族で、数年に一度の転勤があります。
2人の娘がいまして、2人とも繊細な気質を持っているので「転校」にはかなり慎重に取り組んできました。
今では2人とも、自分の得意をのびのびと発揮しながら、毎日楽しく学校に通っています。
この記事では、これまでわが子が転園4回・転校2回(※)した経験と、多くの転勤妻から話を聞いたことをもとに、転校の準備について書いていきます。 ※2人の合計
なお、準備の内容は行政手続き関連ではなく、子どものメンタルに特化したものです。
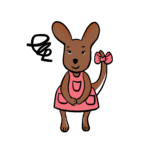 キャサリン
キャサリン転校て、とっても不安よね…
自分が子どもの頃に経験したことがないから、
自分も子どももどうしたらいいのか、本当にわからなくて…
いじめられたらどうしよう、不登校になってしまったら…など
マイナスなことばかり考えてしまうわ
そう、たぶん「わからないから不安」なのよね。
そして、その不安な気持ちが子どもにも伝わってしまって、
家族みんなで不安になってしまう…
「こうすれば大丈夫」という準備と段取りがわかれば、
先の見通しが持てるから、前向きに転校に取り組めるのよね。
ぜひこの記事を最後まで読んで、転校の全体像と攻略法を手に入れてくださいね。
「転校が心配」なら、心配な要因をつきとめよう
「転校が心配」について少し紐解いてみたいと思います。
心配とは、その正体のほとんどが漠然とした不安です。
「今日の夕飯の支度がめんどくさい」とは思っても、「今日の夕飯が不安」とは思わないですよね。
それは、今日の夕飯については「献立を考えるのがめんどくさい」「買い物に行きたくない」などとやりたくないという気持ちはあっても、やり方はわかっているからです。
不安という気持ちは、その全体像がよくわからない時に湧き上がってくる気持ちです。
それなら、「転校」についてよく知ることができ、それに備えて準備することができれば、「心配」な気持ちは減っていきそうですね。
転校について知っておく
転校とは、ご承知の通り「学校を変わる」ことですね。
そして、私たちが知りたいのは「学校を変わること」でどんな問題が起きるのか、ということですよね。
転校でおこりうる問題というのは、ざっくり言うとこの3つです。
- 誤解 出会いの場面で誤解をまねきやすいこと
- 居場所 子どもが精神的、物理的な居場所を失うこと
- 家庭の危機 子どもにとって安全地帯でありたい家庭も不安定になりやすいこと
以上です。
転校したからいじめられるわけではありません。転校したから不登校になるわけでもないんですよね。
転校で誤解が生じてしまったことが原因でいじめにつながってしまうことがあるかもしれませんが、因果関係としては離れています。転校してすぐにいじめられるということはまずないと思います。
また、転校で居場所を失ってメンタルが落ち込んでしまって不登校になってしまうことがあるかもしれませんが、これもその過程で親がサポートしてあげることは充分可能です。
では、転校で生じる3つの問題について、ひとつずつ見ていきましょう。
転校で生まれやすいのは「誤解」
「転校」特有の問題というのが、「誤解」が生まれやすいということです。
転校生を受け入れるクラスメイトと、転校する本人との間で、誤解が生じやすいのです。
クラスメイト…転校生に過度な期待や警戒心を持って接してしまう
転校生本人 …緊張のあまり自分を表現しにくいことがある
言葉や持ち物が違うことや、一度に大量のクラスメイトと会うことで戸惑う姿が周囲に誤解を生みやすい
例えば、転校生を受け入れる側のクラスメイトの視点を想像してみましょう。
「今度の転校生はカワイイらしいよ」「転校生って頭がいいよね」など、事前に噂がたったりします。
小学生低学年くらいですと、悪気なく転校生へ過度の期待が生まれたりします。過度な期待から「思ってたよりかわいくないね」「転校生、頭悪かったんだ」などの心ない発言につながる可能性があります。
では、小学校高学年や中学生の場合はどうでしょうか。
高学年になると今度「警戒心」を抱くようになります。自分のクラスでの立ち位置を脅かす存在が来るのではないかと警戒するのです。
では、転校生本人はどうでしょうか。
転入の日をイメージしてみましょう。
出来上がったクラスの中に、自分ひとりでポツンと入っていきます。
そんな緊張の極限状態で、笑顔で明るく自己紹介なんてできっこありません。なんとか自分の名前と「よろしくお願いします」と言ってみました。向こうはすぐに名前をよんで話かけてきてくれたけれど、こちらはいっぺんに30人もの名前と顔を覚えるのは難しいものです。言葉もなんだかよく聞きとれないし、持ち物も違います。
本人は一生懸命、みんなについていこうと思っているだけ。
でも、クラスメイトからは「なんか転校生、話かけても返事しないし感じ悪いよね…」と思われてします。
これが転校でおきやすい「誤解」ですね。
なんだか切なくなってしまいますね。
でも大丈夫です。対策を後述していますので、最後までお読みいただけたら幸いです。
転校の辛さは「居場所の喪失」
転校で辛いのは「居場所の喪失」です。
仲良しだったお友だち、安心して楽しく通っていた学校、よく遊んだ公園、信頼していた習い事の先生…
こういった、安心して自分らしく過ごせる場所や相手を一気に失ってしまうことが辛いのです。
子どもは特に、学校と家の占める割合が多いため、学校を変わるということは、自分の世界を失うに等しいくらいに強烈なことです。
転校の盲点は「家庭の危機」
そして、転校には以外な盲点があります。
それは家庭の危機です。
「転校」をする場面というのは、家族も変化の局面に立たされている場合が多いのです。
自然災害からの避難で転校するのかもしれません。
離婚や同居など家族のカタチが変わることに伴う転校かもしれません。
転勤による転校の場合でも、パパは単身赴任かもしれませんし、家族一緒の引っ越しであっても、親自身が転居による疲労やキャリアチェンジ、慣れない土地での生活でパニック状態であることが多いものです。
子どものメンタルにまで正直手が回らない…という人も少なくありません。
実は私、ばるママも引っ越しの度にパニック状態になってしまいます。引っ越しで体力を消耗しますし、新生活を組み立てるのはなかなかハードなものです。実際、引っ越し後1年間くらいは、生きているのが精いっぱいという感じです…
親が子どもにしてあげられることはこの3つ プラスα
転校で起こりやすい問題3つを見てきました。
・誤解 出会いの場面で誤解をまねきやすいこと
・居場所 子どもが精神的、物理的な居場所を失うこと
・家庭の危機 子どもにとって安全地帯でありたい家庭も不安定になりやすいこと
なんだか余計に心配になってしまいましたか?大丈夫です。問題が明確に分かれば、あとはそれに対する対策をするだけです。
子どもを観察しよう
まずは、子どもを観察しましょう。そして、タイプを見極めましょう。
なぜなら、子どものタイプによって「転校」がどれくらいハードなことかというのが変わってくるからです。
お子さんは、はじめて会った人にも無邪気に明るく挨拶ができるタイプですか?
それとも、新しい環境ではじっくり周りを観察してからでないと上手く自分を出せないタイプでしょうか。
仮に、前者を「楽観的なタイプ」後者を「繊細なタイプ」とします。
お子さんが楽観的なタイプでしたら、転校のハードルはそこまで高くありません。
もしお子さんが繊細なタイプだとしたら、転校は一大事です。怖がる必要はありませんが、万全な体制で臨む覚悟をしてください。
また、お子さんが楽観的なタイプの子であっても、転校には環境要因が大きく関わってきます。どんなに楽観的な子であっても、一定の負荷がかかっていることを忘れずに、転校前後はよく観察して、話を聞いてあげるとよいと思います。
転校先の担任の先生に協力してもらおう
転校では「誤解が生じやすい」という話をしました。
それには、転校先の先生に味方になってもらうのが得策です。
昨今は個人情報保護や、パワハラセクハラ防止などから、先生側からは家庭の事情につっこんだ質問ができないこともあり、先生も「転校生はどんな子かな?」とわからないことが多いそうです。
ですので、積極的にこちらから情報を開示し、協力を求めることができれば先生も喜んでサポートしてくれるはずです。
転校生の親子からサポ―トを求められて、嫌だという先生はまずいないと思います。
・どんな地域から来たか (言葉・方言・文化の違いも含めて)
・何が理由で転校してきて、家族はどのような状態か
・子どもの性格や好きなこと、苦手なこと
・どんな教科書や学習用具を使っていたか。どこまで学習したか。
・子どもが心配していることやサポートして欲しいこと
などを、先生にお伝えしておくとよいと思います。
先生といえども、転校生を受け入れ慣れている方ばかりではありません。
学習用具や進度が学校によって違って子どもが戸惑っていることに気が付かない先生もいらっしゃいます。それらの懸念事項は、親から明るくお伝えしておくといいと思います。
また、学校の規模や言葉の違いに戸惑いがあることなどもお伝えしてもいいですね。
転入前に、親子で先生にご挨拶する機会を設けてもらえたらベストです。
もしできなければ、電話やメールお手紙などでもいいので、事前にお伝えできるとよいと思います。
子どもがたった一人で「敵地」に突入するのではなく、先生という味方がいる場所に行くのなら、子どもにとっても心もちがだいぶ楽になるでしょう。
クラスの子どもたちと誤解が生じそうになった時には、先生が尽力してくれるはずです。
さらに、親と先生が信頼関係で結ばれているということは、子どもにとって大きな安心材料になります。
「クラスに馴染む」ことにこだわらない
転校の辛さは「居場所の喪失」だと書きました。
安心できる場所、自分らしくいられる場所を失うというのは本当に辛いことです。
ですから、新しい居場所をつくりましょう。
親はそのサポ―トをしてあげるとよいと思います。
けれど、新しいクラスで自分の居場所をつくるというのは、とても難しい場合が多いです。
日本の学校のクラスというのは、生徒一人ひとりの個性が見えにくいからです。
そんな時は、クラブ活動や係活動、委員会活動、放課後や休日に地域イベントがあればイベントなどに参加してみることをオススメします。
クラスを一歩出て、自分が楽しめる活動で出会った子となら、お友だちになりやすいことがあります。
習っていたスポーツや習い事があれば、新しい土地で習い事を再開してみるのもいいですね。
とにかく、「クラスに馴染む」ことを目標にしないことです。
「クラスに馴染む」ことは最も難しいことだからです。
断言しますが「クラスのみんなと仲良くする」なんて無理ゲーです!
本が好きなら、お昼休みに図書室に行ってみるとか。
好きなキャラクターのついたシャツを着て登校してみるとか。(話のきかっけづくり)
サッカーのチームに入ってみるとか。
子どもの好きなことや、得意なことをきかっけに、少しずつ自分を表現してみましょう。
そして、1人でも安心してお付き合いできる子と出会えたらいいな、ということを目標にサポートをしていきましょう。
転校で居場所を失ったけれど、新しい土地でたった一人でも安心して話をができるお友だちができたら、転校大成功!です。
プラスα
「家庭の危機」でもあることを自覚して、自分もムリをしない
これは耳が痛い人もいるかもしれません。
子どもの転校時は、同時に家庭の危機でもあることを自覚しましょう。
特に、離婚や転職、転勤などで、「自分のせいで子どもに辛い思いをさせている」と思っている人には、少し苦しい話かもしれません。
しかし、「誰のせい」とかは、この際もうどうでもよいことです。
「子どもが転校する」からそのメンタルをサポートする、という事実を見て具体的に対策をしていくだけです。
「転校」自体がいじめや不登校に直接つながるものではありません。
ただ、転校は不確定要素もあり、子どもに一定の負荷はかかります。なので、問題が噴出しやすい場面であることは間違いありません。
そして、子どもが転校するという場面では、親であるあなた自身も辛い状況、大変な状況におかれている場合が多いと考えられます。
まずは、周りの人や、お金で解決できることがあるならそれに、どんどん頼ってこの危機を乗り越えましょう。
転校前後に子どもにかかる負荷を、家庭でしっかり受け止めてあげる覚悟と準備があれば、それは乗り越えられることが多いです。
(でも、転校は環境要因も大きいです。ですので、今辛い思いをしてしまっている方がいても、それはあなたのせいではありません。)
まとめ
ここまで、転校でおこりやすい問題点を整理し、その対策を書いてきました。
【転校でおこる問題】
・誤解 出会いの場面で誤解をまねきやすいこと
・居場所 子どもが精神的、物理的な居場所を失うこと
・家庭の危機 子どもにとって安全地帯でありたい家庭も不安定になりやすいこと
【転校でおこる問題に対する対策】
1.子どもを観察しよう
2.転校先の担任の先生に協力してもらおう
3.「クラスに馴染む」ことを目標にしない
プラスα 「家庭の危機」であることも自覚して、自分も無理をしない
転校したからいじめられるとか、転校したから不登校になるとか、そういうことはありませんのでどうか安心して転校に立ち向かっていっていただきたいと思います。
ただし、転校特有の問題点というのがあることも事実ですので整理してみました。
それについては、粛々と対応をしていけばいいと思います。
転校を乗り越えた子どもは、他の子よりも大きなチャレンジを経験します。
ですから、一回りも二回りも成長します!
多くの転校経験者や、わが子を見ていてそう思いました。
一緒に子どもの転校を乗り越えていけたら嬉しいです!
転校する子どもの親の心構えなら、この本がオススメです↓